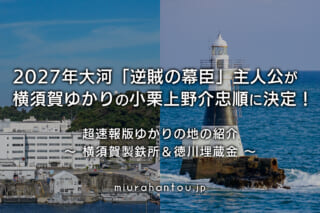伝福寺(傳福寺)は、久里浜港やくりはま花の国のすぐ近くにある、室町時代後期(戦国時代)に創建された寺院です。迷路のように入り組んだ路地の中で、古くからある集落に囲まれるように建っています。
大きな通りに面していないため気づきにくいですが、参道沿いの桜やツツジなど、季節の花々をたのしめるお寺でもあります。
伝福寺は三浦三十三観音・第12番札所と三浦三十八地蔵尊・第7番札所になっていて、それぞれ、千手観世音菩薩立像、地蔵尊半跏坐像が安置されています。
| 山号 | 明星山 |
| 宗派 | 浄土宗 |
| 寺格 | ― |
| 本尊 | 阿弥陀如来 |
| 創建 | 1533年(天文2年) |
| 開山 | 泉蓮社昌誉 |
| 開基 | ― |
伝福寺の境内の一角には、江戸幕府の御用金を積んだまま久里浜沖で沈没したという汽船「早丸」の慰霊碑が建っています。また、幕末から明治初期にかけて活躍した文人画家としても知られ、久里浜や浦賀から三崎方面に抜ける際の難所だった尻こすり坂の開墾に尽力した長島雪操(長島尚賢)の墓もあります。

INDEX
久里浜の海岸エリアの中心的な場所だった伝福寺

戦前に旧日本軍の施設が進出してくるまでの久里浜は、現在の京急久里浜駅/JR久里浜駅周辺(現在の久里浜1・4・5丁目あたり。八幡久里浜)と、伝福寺のある久里浜海岸周辺(現在の久里浜8丁目あたり)の大きく2か所に分かれて、集落が存在していました。
それぞれ江戸時代後期と大正時代に編さんされた地誌「新編相模国風土記稿」や「久里浜村誌」によると、伝福寺は鎌倉・名越の北条政子ゆかりの寺院・安養院の末寺で、近隣には伝福寺の末寺として薬師堂と観音堂(いずれも廃寺)があったことなどが記されています。
すぐ近くに鎮座する、源頼朝も参詣したと言う三浦一族ゆかりの住吉神社とともに、伝福寺は古くから久里浜の海岸エリアの中心的な場所の一つだったことがうかがい知れます。
さらにずっと時代はさかのぼりますが、1981年(昭和56年)に発掘調査が行われた伝福寺遺跡では、約5000年前のものとみられている、神奈川県内で唯一の縄文時代の丸木舟も出土しています。この地域での人の営みは、三浦半島でもトップクラスの深い歴史のあったことが確認されています。
徳川埋蔵金伝説と汽船早丸遭難者追悼碑

海に近い伝福寺は、久里浜の海の生き証人でもあります。久里浜海岸での歴史的な出来事と言えば、ペリーの黒船来航です。
この時代イチの歴史的事件の陰に隠れて、幕末の久里浜の海ではもう一つ大きな出来事が起こっていました。それが、当時仙台藩の所有だった汽船「早丸」の事故です。久里浜沖の海獺島付近で沈没した早丸は、多くの犠牲者を出しました。この犠牲者たちを弔うため、後年、伝福寺の境内に、汽船早丸遭難者追悼碑が建立されました。
この早丸には、徳川埋蔵金の伝説が残されています。
早丸は、江戸無血開城の数日後というタイミングに、横浜港から出航しました。この船に数百両にも及ぶ江戸幕府の御用金が積まれていたと言われています。これが、いわゆる徳川埋蔵金ではないかというのです。
この伝説が広まった昭和・平成、そして令和の時代に入った現在までに、久里浜沖で徳川埋蔵金が見つかったという事実はなく、その信憑性は定かではありません。ただ、幕末~明治維新という激動の時代に、久里浜沖で多くの方が命を落としたという歴史的事実だけは、伝福寺の汽船「早丸」の慰霊碑が静かに語りかけてくれています。
くりはま花の国に隣接した隠れた花の寺

伝福寺は、三浦半島を代表する花の名所の一つであるくりはま花の国の第2駐車場のすぐ近くにあります。伝福寺の境内も季節の花々がよくお手入れされていて、隠れた花の寺でもあります。
とくに、参道沿いの桜やツツジが美しいですが、少し離れた場所(神明第2公園の隣り)にある印塔廟のモクレンも見逃せません。





その他の伝福寺境内の見どころ
本堂

地蔵堂

観世音菩薩

慰霊碑

印塔廟の十三重石塔

伝福寺周辺の見どころ