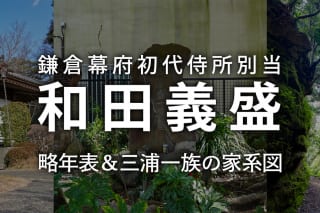聖徳寺坂の中ほどにある永嶋家の長屋門は、門扉等が朱塗りであることから、通称「赤門」と呼ばれています。また、地名にちなんで「田戸の赤門」(現在の住所は安浦町)などと呼ばれることもあります。
この田戸の永嶋家(永島家)は、三浦一族の子孫と伝えられています。戦国時代には浜代官を務め、江戸時代は公郷村の名主(現代の村長に相当。庄屋とほぼ同義)を世襲し、代々当主は「永嶋庄兵衛」を名乗りました。とくに江戸後期は、三浦半島の海防を担った諸藩や浦賀奉行所との調整役など、公郷村村内に留まらず、三浦郡の郡中取締役という役割も与えられた名家でした。田戸の永嶋庄兵衛家を指して、「田戸庄」などとも呼ばれていました。
作家・島崎藤村の小説「夜明け前」に “公郷村に古い屋敷と言えば、土地の漁師にまでよく知られていた。” と出てくるのは、赤門の永嶋家のことです。
島崎家も三浦一族の子孫と伝えられていて、永嶋家の分家にあたります。
島崎藤村は、「夜明け前」執筆にあたり、実際に永嶋家を訪れています。それは小説のための取材という以上に、自らのルーツを探る旅になったのでしょう。小説内で、永嶋家をモデルとした家は、とても重要な役割を与えられています。
INDEX
かつての大津陣屋の長屋門説などがある永嶋家の赤門

長屋門は近世の武家屋敷の表門に多く見られる形式の建築物です。主家を防御する目的で家臣を住まわせた長屋と表門を一体構造にした建築が、武家の長屋門です。
永嶋家(永島家)の赤門は、間口八間(約14.4m)・奥行二間(約3.6m)の木造瓦葺きで、長屋門としては比較的コンパクトな部類と言えます。欅材の門扉は江戸時代のものと推定されていますが、それ以外の部分は明治以降に何度か修復されています。江戸時代末期の建築と伝えられている旧秋谷村の若命家長屋門と同様、腰の部分は幾何学模様のデザインが特徴的な「なまこ壁」と呼ばれる工法が用いられています。
武家ではない名主の永嶋家の屋敷に長屋門がある理由は、明確には分かっていません。苗字帯刀を許されていたため長屋門の建築も許可されたとする説の他、元は大津陣屋(現在の大津中学校や県立横須賀大津高校付近にあった、幕末に江戸内海(江戸湾、現在の東京湾)を警備するために置かれた陣屋)の門だったものがここに移されたとか、明治維新の神仏分離令(廃仏毀釈)まで鎌倉の鶴岡八幡宮寺で山門として使われていたものが移されたといった説もあります。鶴岡八幡宮寺の山門が長屋門だったということはないでしょうから、もしこの説だった場合は、門扉のみ再利用されたということになるでしょう。
また、1915年(大正4年)発行の「浦賀案内記」や明治時代から大正時代にかけて編さんされた「浦賀志録」といった近代の浦賀の地誌には、永嶋家の赤門は三浦郡の大庄屋などを務めた浦島家の門だったものであると書かれています。両書とも、江戸時代後期に編さんされた地誌「新編相模国風土記稿」内の浦島家に関する記載を引用しながら、後北条氏(小田原北条氏)の時代に浦賀に土着し、関東に徳川家康が入った後は県令の長谷川長綱に従い、以降も浦島家は江戸期を通じて地元の有力者として活躍したことが語られています。明治維新後、浦島氏は江戸に出て徒士株(武士の身分)を買いましたが、幕府が崩壊したため失敗し、当時、子孫は箱根で暮らすようになっていたと言います。
永嶋家と浦島家は同じ三浦郡の有力者として長い付き合いがあったでしょうし、この説がもっとも現実味を帯びていると言えるかもしれません。
](https://miurahantou.jp/wp-content/uploads/2025/11/6719dbc68435074b6f5cb4ede1b2da6d-1200x800.jpg)
「左 横須賀 金沢道」「右 大津 浦賀道」と刻まれた浦賀道道標
赤門の向かって右側には、浦賀道(東海道・保土ヶ谷宿から金沢を経由して横須賀の東京湾側に沿って浦賀に至る「東浦賀道(東回り浦賀道)」)を示す1862年(文久2年)に建てられた円柱型道標があります。この浦賀道道標には、「左 横須賀 金沢道」「右 大津 浦賀道」などといった行き先が刻まれています。
道標の建つ場所は当初より移動しているようですが、この道標が示すとおり、赤門の前の通りはかつての浦賀道でした。
安浦町や平成町の埋め立てによって、現在は海から遠く離れていますが、江戸時代の海岸線は永嶋家(永島家)の屋敷の前まで迫っていました。金沢・横須賀方面から主に内陸の山地を通っていた浦賀道は、この場所で海に出て、海岸線に沿って大津・浦賀方面に向かっていました。
なお、安浦町の埋め立て事業は、明治後期、永嶋家によって赤門前の海岸を埋め立てることからはじまりました。
しかし、この埋め立て事業は難航を極め、1916年(大正5年)には永嶋家はこの事業から手を引き、その権利は安田保善社(当時は「保善社」という名称。現在の安田不動産)に譲渡されることとなり、1922年(大正11年)にようやく完成しています。



「太平記」にも登場する三浦義勝を祖とする永嶋家

前述の「新編相模国風土記稿」によれば、永嶋家(永島家)の先祖は、三浦大田和平六左衛門尉義勝であるとしています。大田和氏(大多和氏)は、平安時代後期から鎌倉時代前期に活躍した武将で三浦大介義明の子の大多和義久を祖とする氏族です。
三浦義勝(大多和義勝)は、軍記物語「太平記」に登場し、鎌倉幕府倒幕の立役者の一人として描かれています。
鎌倉時代末期の1333年(元弘3年)、新田義貞率いる反幕府勢と鎌倉幕府勢が争った分倍河原の戦いで、三浦義勝は他の相模国の武士を誘い、劣勢だった新田勢に寝返り、先陣をきって戦った結果、新田勢に勝利をもたらしました。この分倍河原の戦いの勝利で戦局は新田勢優勢に大きく傾き、この1週間後に、鎌倉幕府は滅亡を迎えることになります。
その後の三浦義勝は、今度は北条氏得宗家(本家)最後の当主・北条高時の遺児である北条時行に従い足利尊氏と戦いますが、これに敗れ、楠木正成の配下に属すことになります。南北朝時代の1339年(暦応2年)に義勝は三浦半島へ帰住し、90歳まで生き、大矢部の三浦一族ゆかりの円通寺(廃寺)に葬られたと言います。
永嶋(永島)姓を名乗るようになったのは、三浦義勝の子・義政からです。しかし、義政は若くして亡くなってしまったため、義勝は楠木正成の四男を婿に迎え、この正徳が永嶋家を継ぐことになります。
このように、永嶋家は、三浦一族だけでなく、楠木家の子孫でもあります。
木曽に移った島崎家と三浦太夫/朝比奈義秀の伝承

この永嶋家(永島家)の子孫の中から木曽に移り住んだ者がいて、それが明治時代から昭和前期に活躍した作家・島崎藤村の祖先にあたります。
1915年(大正4年)に発行された長野県西筑摩郡(現在の木曽郡)の地誌「西筑摩郡誌」内の「木曾人物誌」という章には、島崎藤村の父で国学者だった島崎正樹が紹介されています。この「西筑摩郡誌」の島崎正樹の項によると、戦国時代の1513年(永正10年)、島崎監物重綱が木曽家に仕えて移住したのが、木曽の島崎家のはじまりと伝えています。
なぜ、永嶋家の子孫が木曽家に仕えたのかはよく分かりませんが、「西筑摩郡誌」では、やはり「木曾人物誌」で紹介されている三浦太夫が三浦一族の朝比奈義秀であるという説をとっていて、木曽には島崎家の移住より古くから三浦氏との関わりが伝えられています。
朝比奈義秀は和田義盛の三男で、鎌倉時代前期、執権北条氏らによって和田一族が滅ぼされた和田合戦(和田義盛の乱)後に行方不明になっています。「西筑摩郡誌」は、木曽に落ち延び、三浦山と呼ばれる山中に居住してこの地を開拓したと伝わる三浦太夫こそ朝比奈義秀その人だとしています。また、朝比奈義秀の母は木曽義仲の妾でもあった巴御前だとしていて、これもその根拠の一つに挙げています。
島崎藤村「夜明け前」の中の永嶋家

“木曾路はすべて山の中である。” という有名な書き出しではじまる「夜明け前」は、島崎藤村が1929年(昭和4年)から1935年(昭和10年)にかけて発表した小説で、幕末から明治維新の史実を背景に、自らの父・島崎正樹をモデルとした主人公「青山半蔵」の生涯を描いた大作です。日本の近代小説の金字塔と称されることもあります。
この「夜明け前」の中で、永嶋家(永島家)は「山上家」として登場します。
物語は、中山道の馬籠宿(現在の岐阜県中津川市馬籠)で本陣・庄屋・問屋の三役を兼ねる家に生まれ育った青山半蔵の日常生活が語られるところからはじまります。遠く、浦賀に黒船が現われて、久里浜(小説内では「久里が浜」)にアメリカの水師提督ペリーが上陸したといううわさを耳にしますが、木曽の山村に暮らす半蔵には詳しい様子を知るすべもありませんでした。
馬籠宿の隣りの妻籠宿(現在の長野県木曽郡南木曽町)の本陣は、青山半蔵の実家筋にあたる家が務めていました。この宿に、相州三浦・横須賀在・公郷村に住む山上家の当主・山上七郎左衛門が訪ねてきて、お互い三浦一族の子孫であることなど、両家の歴史を語っていったのを境に、物語は大きく動き出すことになります。
青山半蔵と妻籠宿・本陣の青山寿平次は、すぐに、二人で公郷村の山上家を訪ねる計画を立て、実行に移します。
半蔵らはまず中山道で江戸に出て、金沢から横須賀までは海路を使い、公郷村まで訪れています。金沢と横須賀の間の浦賀道(東回り浦賀道)は十三峠などの難所を越える必要がありました。木曽路周辺の難所と比べればたいしたことはないはずですが、この頃の金沢・横須賀間は海路を使うのが一般的だったということが、それとなく描かれています。
山上家を訪れた青山半蔵は、自らの祖先がどのようにして三浦半島から木曽の西の外れまでたどり着いたのかという出自についてや、実際にペリーが上陸した場所の近くまで来ていることを実感しつつ、海の向こうから押し寄せてくる列強諸国に思いをめぐらすのでした。
前述のとおり「夜明け前」の主人公・青山半蔵は島崎藤村の父・正樹がモデルですが、この山上家訪問のシーンは、藤村自身が半蔵に乗り移っているようにも感じます。藤村は「夜明け前」執筆前に永嶋家を訪問していますが、それは藤村自身の未知のルーツを探る旅でもあったはずで、藤村自身が経験した感想が多分に反映されているだろうからです。
小説内の山上家訪問のシーンは、以下のような描写で終わっています。
“まったく、木曾の山村を開拓した青山家の祖先にとっては、ここが古里なのだ。裏山の崖の下の方には、岸へ押し寄せ押し寄せする潮が全世界をめぐる生命の脈搏のように、間をおいては響き砕けていた。半蔵も寿平次もその裏山の上の位置から去りかねて、海を望みながら松林の間に立ちつくした。”
おそらくこれは、島崎藤村が永嶋家を訪ねたときに感じたことを、そのまま描写したものなのではないでしょうか。
「夜明け前」は、小説が発表された昭和前期からおよそ80~60年前の時代の出来事を描いていて、当時の現代史を描いた歴史小説とも言えます(80~60年前というのは、2020年代の令和の時代からみた場合、第二次世界大戦中から戦後の復興期ごろまでが該当します)。まだその時代に生きていた当事者から直接取材できるギリギリの古さということもあってか、歴史小説としてリアリティがあり、生々しくもあります。
たとえば、小説内でたびたび言及される黒船来航に関する描写も、永嶋家から聞いた内容が含まれているのかは分かりませんが、実際に幕末を生きた人々から直接聞いた話もあるのでしょう。
また、安政の大獄で謹慎の処分を受けた岩瀬忠震(小説内では「岩瀬肥後」)や、戊辰戦争勃発後に反逆の罪で斬首された小栗忠順(小説内では「小栗上野」)など、「逆賊の幕臣」と捉えられ、明治期には評価されていなかったと考えられる人物も、「夜明け前」の中で島崎藤村は、今の時代から見ても現代的な評価を与えています。
日米修好通商条約締結において、岩瀬忠震は幕府全権として交渉に臨み、通商条約が未経験の当時の日本にあって、中国やその他のアジア諸国のような欧米列強による勢力圏争いに巻き込まれることを回避し、最善を尽くしたと言えます。
幕府の勘定奉行だった小栗忠順は、徳川政権の行く末を知りながらも、将来の日本の近代化のために、横須賀造船所(小栗の時代は「横須賀製鉄所」という名称)建設を強く推し進めました。
赤門(田戸の永嶋家長屋門)周辺の見どころ











](https://miurahantou.jp/wp-content/uploads/2025/11/2b9f95126e26864aeee338d4d2077abf.jpg)