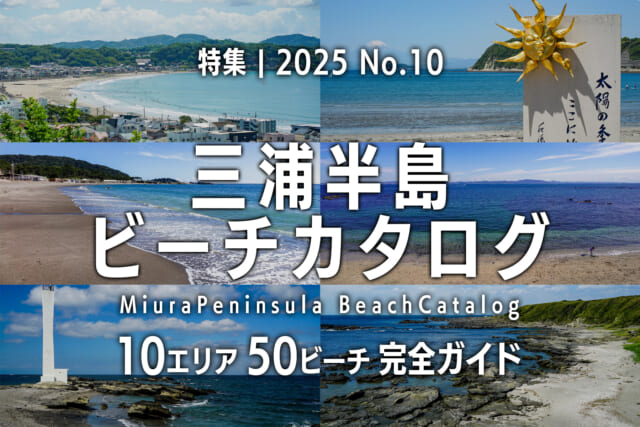三崎・小網代の白髭神社は、小網代湾の最奥に鎮座する旧小網代村の鎮守です。富士山を望む景勝地にあって、小網代の森から続く杜の中で、小ぶりな朱塗りの社殿がよく映えています。
三浦七福神の第五番・長安寿老人の札所になっていて、例年1月1日から10日ごろまで御開帳されます。
白髭神社の創建は室町時代後期の天文年間(1532年~1555年)とされていて、小網代村の漁夫が、夜中、網にかかった霊光まぶしく光る束帯姿の御神体を持ち帰り、中筒男命として祀ったのがはじまりと伝えられています。
中筒男命は住吉三神(住吉大神)の一柱で、海の神や航海の神として知られています。
| 主祭神 | 中筒男命(長安寿老人) |
| 旧社格等 | 村社 |
| 創建 | 天文年間(1532年~1555年) |
| 祭礼 | 4月7日 春季例祭 7月20日 夏季例祭 10月24日 新嘗祭 ※実際の日にちは異なる場合があります |
白髭神社は、関東でも貴重な自然環境が残る、小網代の森の南端に位置しています。小網代の森の宮ノ前峠入口までは徒歩で5分ほどです。小網代の森の象徴と言えるアカテガニは、白髭神社周辺の崖地でも見ることができます。
白髭神社の社叢林は、小網代の森から連続している杜です。イチョウやクスノキの大木から松や藤などの低木まで、神社境内として植林された木々を多く見ることができます。小網代の森の自然環境とは異なる性質のものですが、うっそうと茂る杜は神域らしい荘厳とした雰囲気を感じられます。

INDEX
小網代湾の奥深くで航海の神を祀る白髭神社

白髭神社の鎮座する小網代湾は、富士山を望む、相模湾から深く内陸に入り込んだ地形の良港で、古くから廻船寄港地や三崎の避難港という位置づけでした。小網代湾は、現在も、漁港やマリーナとして利用されています。
白髭神社も、古来、このような商船や漁船の船乗りたちが、航海の安全を願って祀られたのがはじまりで、後の時代に住吉三神と結びついて現在にいたるのでしょう。
横須賀・野比の白髭神社をはじめ、全国の白髭神社は猿田彦神を御祭神として祀るのが一般的です。道案内の神様とされる猿田彦神も、航海の神様である住吉三神にも通じるところがある存在で、結びつけられた日本神話の神こそ違いますが、いずれも神社の起源としては共通したものであったと考えられます。

三浦七福神・第五番の長安寿老人
白髭神社にはまた、三浦七福神の長安寿老人も祀られています。江戸時代後期に編さんされた地誌「新編相模国風土記稿」や1935年(昭和10年)に発行された「三浦郡神社由緒記」などには関連した記述が見られないため、もともと存在していた白髭神社の由緒をもとに、近現代に結びつけられた神様であるとみられます。(三浦七福神の開設は1965年(昭和40年))
長安寿老人は中国の民間信仰で南極星の化身とされていて、不老長寿の徳があると言われています。この御神徳から連想される姿は、白髭神社の「白髭」にピッタリ合っていると言えます。

白髭神社に奉納されたカンカン石とオオシャコガイの手水鉢

白髭神社の社殿前には、「鳴石」や「カンカン石」と呼ばれる長細い石が奉納されています。叩くとカンカンという金属性の音がするため、このように呼ばれています。これは、まだ金属製の錨が貴重だった時代におもりとして使用していた「きこいかり」という石です。その昔、白髭明神がこの石をほしいというので、摂津国(現在の大阪府北中部の大半および兵庫県南東部)の船頭が奉納したものと伝えられています。
摂津国の一宮(もっとも社格の高い神社)は全国の住吉神社の総本社・住吉大社であり、住吉三神の中筒男命を祀る白髭神社には、摂津国の人々がなんらかの影響を与えていたのかもしれません。
また、白髭神社の手水舎には、立派なオオシャコガイの手水鉢が奉納されています。
これも、古くから白髭神社が漁業や海と密接な関係にあったことを象徴するような品と言えます。


白髭神社(小網代)の境内社
白髭神社には、市杵島姫命・天照皇大神・日本武尊が合祀されています。
それぞれ、旧小網代村に鎮座していた、厳島神社(城ノ内)・神明神社(宮ノ前)・御嶽神社(東之台)の御祭神です。

三浦市保護樹木のフジをはじめとした白髭神社周辺の自然

白髭神社の境内では、イチョウやクスノキなどが大木に育ち、社叢林を形成しています。
ゴールデンウイークごろになると、紫色のフジの花が目立つようになります。これらの木は「白髭神社のフジ(紫・白)」として、三浦市保護樹木に指定されています。白髭神社の境内以外にも、フジは小網代湾沿いの崖地で多く目にすることができます。
晩秋になると、境内の奥に立つイチョウの大木が黄金色に輝きます。イチョウも十分大木なのですが、さらに大きな木に囲まれているため、境内の外側からはあまり目立ちません。この隠れイチョウのせいで、晩秋の白髭神社は社叢林の中にいるほうが明るく感じる、不思議な境内です。


白髭神社(小網代)周辺の見どころ