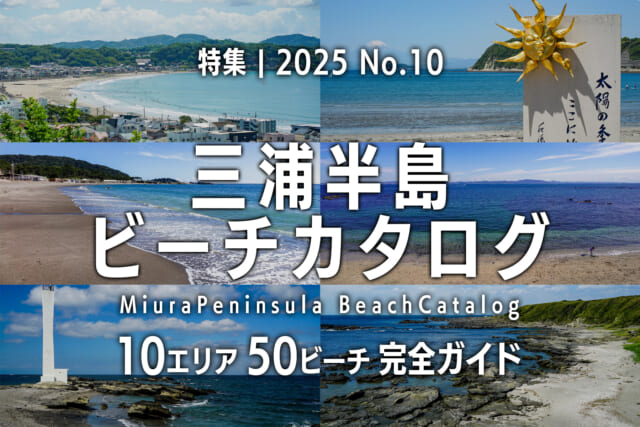久里浜天神社は、現在の久里浜エリアの平野部を開墾した砂村新左衛門が、江戸時代前期の1660年(万治3年)に摂津国(現在の大阪府北中部周辺)の福島天満宮の御祭神・菅原道真を勧請して創建した神社です。
当時の久里浜は、東京湾から深く入り江が入り込んでいて、その周辺も湿地帯が続いているような場所でした。この場所に、現在の平作川の元になる川を整備して、新田開発したのが、砂村新左衛門でした。
久里浜天神社は、砂村新左衛門が内川新田開拓工事の加護を願い、創建されました。
毎年12月5日に開かれている久里浜天神社の酉の市は、久里浜エリアに年の瀬を告げる冬の風物詩で、開運を求める人々で夜遅くまで賑わいます。
| 主祭神 | 菅原道眞 |
| 旧社格等 | ー |
| 創建 | 1660年(万治3年) |
| 祭礼 | 1月1日 歳旦祭 1月3日 元始祭 1月15日 左義長「どんと祭」「古神札焼納祭」 1月15日 成人祭 1月25日 初天神 2月11日 紀元祭 2月17日 祈年祭「春祭り」 2月23日 天長祭 2月25日 梅花祭 4月20日 明祭 5月25日 正五九祭 6月25日 御誕辰祭 6月30日 大祓 6月30日 古神札焼納祭 8月10日に近い土曜 例大祭「湯立神楽」 8月10日に近い日曜 夏季大祭「お天王祭」 9月9日 余香祭 9月25日 正五九祭 10月17日 神嘗祭当日祭 10月20日 地久祭 11月3日 明治祭 11月15日 七五三祈請祭 11月23日 新嘗祭「秋祭り」 12月5日 酉の市祈請祭 12月31日 大祓 12月31日 古神札焼納祭 12月31日 除夜祭 毎月1日 月首祭 毎月15日 月次祭 ※実際の日にちは異なる場合があります |
学問の神様として親しまれている菅原道真を主祭神として祀る神社は、三浦半島エリアでは「三古天神社」の一つに数えられることもある(諸説あり)、鎌倉の荏柄天神社が有名です。鎌倉以南の三浦半島では、久里浜天神社が唯一の菅原道真を主祭神として祀る神社です。



INDEX
菅原道真が牛にまたがる「牛乗り天神像」

久里浜天神社の鳥居をくぐると、すぐ右手に迎えてくれるのが、「牛乗り天神像」です。菅原道真を祀る神社に「御神牛」として牛の像があったり、菅原道真公自身の像がある例はめずらしくありませんが、菅原道真が牛に乗っている像というのは、とてもめずらしいです。
菅原道真は丑年の丑の日生まれだったということで、牛をかわいがっていたと言われています。また、道真が亡くなったのも丑の日でした。
久里浜天神社の「牛乗り天神像」も、一般的な「御神牛」と同じように、自分の身体の悪い場所と同じ牛の部位を撫でると治ると言われています。

初春に境内を彩る紅白の梅の花

梅の木も、菅原道真を祀る神社の定番です。こちらも、道真が梅の花を好んでいたという言い伝えから来ています。
久里浜天神社でも、毎年、受験シーズンにあわせるように、2月ごろ、社殿の両脇や鳥居の近くなどで、紅白の梅をたのしむことができます。

▼その他の横須賀の梅の名所はこちら▼

内川町内会として残る内川新田開拓の名残

内川新田開拓の成功を祈願して久里浜天神社を創建した砂村新左衛門でしたが、三浦半島最大の湿地帯の開発は、難航を極めました。とくに、現在の夫婦橋のもとになった水門の工事はたいへんだったようで、新左衛門の夢枕に現われた菅原道真と福島天満宮に祀られている天照皇大神の夢のお告げによって、ようやく完成させることができたと言います。
この霊夢に感謝した砂村新左衛門は、1665年(寛文5年)、水門に近い明浜(旧字名)の地に水神社を勧請しました。
水神社は、1908年(明治41年)、久里浜天神社に合祀されました。明浜という地名も、村の統合や町名の整理などによって見られなくなりましたが、近くの明浜小学校という学校名として残っています(明浜小学校は、戦後、久里浜小学校から分離した学校のため、古い学校というわけではありません)。
また、内川新田開拓によって平作川流域にできた内川新田といった地名も、そのもととなった内川という地名も、現在ではかなり狭い範囲を示す町名となりましたが、久里浜天神社が鎮座する久里浜5丁目周辺は現在も内川町内会と称しています。
砂村新左衛門の墓は、久里浜天神社から徒歩約10分ほどの場所にある、正業寺にあります。
毎年12月5日に夜まで賑わう久里浜天神社の酉の市

一般的に「酉の市」は11月の酉の日に行われる、商売繁盛や金運・開運などを願うお祭りですが、久里浜天神社の酉の市は毎年12月5日と日にちが決まっています。
久里浜天神社の酉の市では、金運と開運を招くご利益があるという「金運開運招福熊手」が人気です。
例年、お昼ごろから、久里浜天神社の境内と、その前のイオン久里浜店との間の歩道沿いに、たくさんの露店が建ち並んで、夜21時ごろまで賑わいます。


久里浜天神社境内のその他の見どころ
祖霊社

稲荷社

石塔・庚申塔群

安産子宝いぬ

久里浜天神社周辺の見どころ









▼その他の横須賀のパワースポットはこちら▼