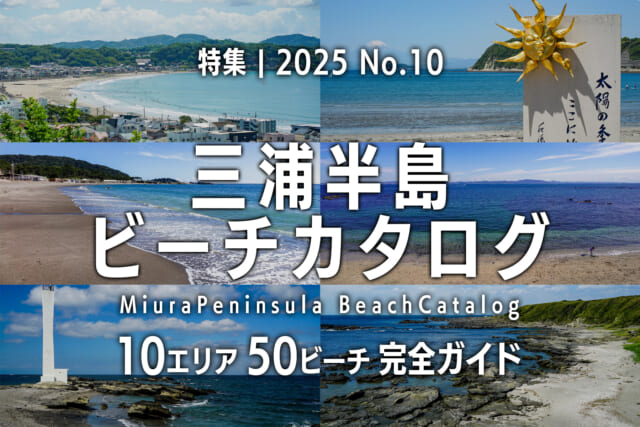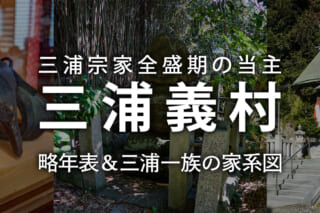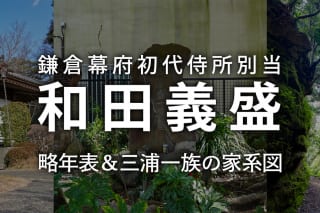三浦義澄(幼名:荒次郎、次郎)は、鎌倉幕府創設期の三浦一族の当主です。
荒次郎や次郎といった幼名からも分かるように、三浦義澄は、1180年(治承4年)の源頼朝挙兵時に衣笠城で討ち死にした三浦大介義明の「次男」ですが、「長男」の兄・杉本義宗は1164年(長寛2年)に若くして戦死しているため、義澄が三浦氏宗家(本家)の家督を継ぎました。あるいは、杉本義宗は三浦氏ではなく杉本氏を名乗っているため、その資質を買われてのことか、兄が亡くなるより早い時期に、義澄が三浦氏宗家を継ぐことになっていたと考えられます。
INDEX
鎌倉幕府草創期に活躍
三浦義澄は、源頼朝の挙兵直後の衣笠城合戦で討死した父・義明から三浦一族の当主を引き継ぎ、その後の平家方との戦いで武功を挙げ、鎌倉幕府成立後は最有力の御家人の一人になりました。
頼朝の死後も、第2代将軍・源頼家を補佐する「十三人の合議制」のメンバーに選ばれ、その権力は子の三浦義村に引き継がれていきました。
三浦大介義明の子であり三浦義村の父である三浦義澄は、歴史上、地味な存在ですが、鎌倉幕府の創設には欠かせない存在でした。
源頼朝が平家討伐の兵を挙げる直前、三浦義澄は、京からの大番役の帰りに伊豆の源頼朝のもとに立ち寄っています。このときに、挙兵時の三浦一族の協力の約束と段取りが話し合われたと推察されます。しかし、挙兵後、初戦で両者は合流することができず、プランBに移ることになります。房総半島の安房国で落ち合った源頼朝らと三浦義澄ら三浦一族は、東京湾を一周しながら勢力も急速に拡大させ、鎌倉入りを果たすことになります。このときの頼朝の快進撃の中心にいたのが、三浦一族であり、三浦義澄でした。頼朝が本拠地に鎌倉を選んだ理由の一つには、もっとも信頼がおける勢力であった三浦一族の所領に隣接していたということもあったでしょう。
その後の平家との戦いや奥州征伐でも、三浦義澄は派手な武勇こそ伝わっていませんが、一族を率いて、最前線でも、後方支援としても、源頼朝の勝利に大きく貢献しました。
源頼朝の死後、鎌倉幕府の将軍(鎌倉殿)を継いだ源頼家の最側近だった梶原景時失脚につながることになる梶原景時の変では、子の三浦義村が中心的な役割を果たしました。鎌倉を追放された梶原景時は、その翌年、京へ向かう途中、駿河国で襲われ、敗死しました。
三浦義澄の最期は、この、三浦義村が歴史の表舞台に現われる最初の出来事となった事件を見届けるように、梶原景時の死の3日後に息を引き取りました。病死でした。
三浦義澄の墓は、父・義明の墓がある満昌寺や子・義村を祀っている近殿神社の近くの、薬王寺旧跡にあります。



和田義盛が創建した薬王寺

薬王寺は、1212年(建暦2年)に、鎌倉幕府の侍所別当であった和田義盛が、父・杉本義宗や叔父・三浦義澄の菩提を弔うために創建したと伝わっています。
もしこれが事実であれば、和田義盛はその翌年に亡くなるため、最晩年の仕事ということになります。義盛は三浦半島を中心に多くの寺院を建立しましたが、自身のルーツと言える二人のための寺院をこの時期に建てたのには、三浦一族に対して何か思うところがあったのでしょう。
和田義盛の最期は、三浦義澄の子であり三浦一族の当主となっていた三浦義村の裏切りにもあい、北条義時の軍勢と戦い、討死しました。
薬王寺は、1876年(明治9年)頃に廃寺となり、現在は三浦義澄の墓といくつかの石碑や石塔だけが残っています。
| 山号 | 仏頂山 |
| 宗派 | ― |
| 寺格 | ― |
| 本尊 | 薬師如来像 |
| 創建 | 1212年(建暦2年) |
| 開山 | ― |
| 開基 | 和田義盛 |
薬王寺の遺構
駒繋石(こまつなぎいし)

薬王寺の山門があった場所には、そのことを示す石碑と、薬王寺にお参りする時に馬の手綱を繋いだとされる「駒繋石」があります。
「三浦札所四番 薬師如来 薬王寺」の石碑

三浦義澄の墓の入口に建つ「薬王寺旧跡」の石碑の裏側に、「三浦札所四番 薬師如来 薬王寺」の石碑が残されています。
三浦義澄の墓脇の石塔群

三浦義澄の墓の脇には、複数の石仏や石塔などが残されています。
三浦義澄の墓や薬王寺旧跡へのアクセス
三浦義澄の墓や薬王寺旧跡は、大通りから奥まった住宅地の路地の中にあるため、場所が少しわかりにくいです。
大通り(久里浜田浦線)からの入口

満昌寺などがある大矢部1丁目の久里浜田浦線の北側(「市営公園墓地入口」信号の近く)に、「薬王寺旧跡」の案内板の矢印が示す方向に、大通りから斜めにのびる細道があります。この、明らかに古道とわかる細道を20mほど進むと、右側に駒繋石と山門跡を示す石碑が建っています。おそらくこの道が参道だったのでしょう。
この道を奥へと進むと、また「薬王寺旧跡」の案内板が見えてきますので、矢印の方向に進むと、薬王寺旧跡の案内板や三浦義澄の墓などがあります。
近殿神社からの順路

近殿神社から住宅街の路地の旧道をたどって行くこともできます。近殿神社の鳥居の前から境内を見て右側に進むと、1分ほどで着きます。