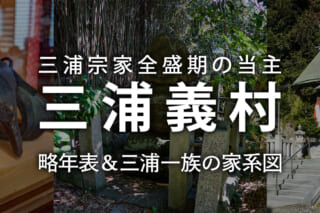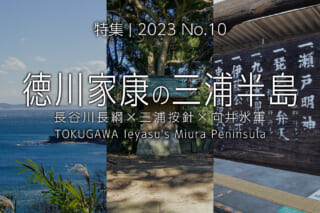乗誓寺は、鎌倉時代初期に起きた「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我十郎祐成(兄)の子・了源(平塚入道)が平塚に一宇を建てたのがはじまりと伝わる、東浦賀の寺院です。
当初は「阿弥陀寺」と号していましたが、浦賀へ移転後の江戸時代前期に、今の「乗誓寺」に改められました。
乗誓寺住職は、平塚時代より浦賀に移ってから現在に至るまで、代々世襲制で曾我十郎祐成の子孫が受け継いできていると言います。
| 山号 | 東教山 |
| 宗派 | 浄土真宗本願寺派 (西本願寺) |
| 寺格 | ― |
| 本尊 | 阿弥陀如来像 |
| 創建 | 1227年(安貞元年) |
| 開山 | ― |
| 開基 | 了源(平塚入道) |
江戸時代後期に活躍した浮世絵師・歌川広重(安藤広重)は、乗誓寺の裏山付近からいくつかの描いたと言います。広重による『日本湊尽』の「相州浦賀」、『山海見立相模』の「相模浦賀」、『武相名所旅絵日記』の「浦賀総図」は、いずれも乗誓寺の建つ東浦賀の山上から浦賀港を望む構図で、港に停泊する舟とともに、港沿いにぎっしりと建ち並ぶ家々が、江戸時代の浦賀の繁栄を物語っています。
INDEX
乗誓寺は曾我兄弟ゆかりの寺
寺伝によると、乗誓寺(当時の阿弥陀寺)を開いた了源(平塚入道)は、鎌倉時代初期の武士・曾我十郎祐成と大磯の遊女だったという虎御前の子とされています。
鎌倉時代初期の1193年(建久4年)、源頼朝が催した富士の巻狩の際に、曾我十郎祐成と弟の曾我五郎時致は、父・河津祐泰の仇である工藤祐経を討ち果たします。いわゆる「曾我兄弟の仇討ち」と呼ばれる事件です。
これから20年近く前になる、平安時代末期の1176年(安元2年)、工藤祐経は、所領である伊豆国伊東荘をめぐって争っていた伊東祐親を暗殺しようと企てますが、失敗し、その場にいた祐親の子で祐成・時致兄弟の父である河津祐泰が討ち死にしました。その後、祐経の妻、祐成・時致兄弟の母は相模国曾我荘(現在の小田原市)の領主・曾我祐信と再婚したため、祐成・時致兄弟は曾我姓を名乗ることになります。
軍記物語「曽我物語」では、「曾我兄弟の仇討ち」に至る経緯や仇討のその後を軸に、伊豆国で挙兵し鎌倉幕府を創設する源頼朝ら、この時代の有力者や著名人の動向も交えつつ、ストーリーは展開されていきます。歴史書ではありませんが、物語は概ね史実に基づいています。
その中には、曾我祐成と虎御前の決して成就することがない恋模様も描かれています。曾我兄弟が仇討を果たした後の「曽我物語」は、虎御前がほぼ主人公のようになり、曾我兄弟を追善する様子などが語られます。

曾我兄弟と三浦一族
「曽我物語」では、曾我兄弟が何度も三浦を訪れる様子が描かれています。まるで、幕府がある鎌倉近くの拠点として利用しているように。
曾我兄弟は、三浦氏宗家(本家)第6代当主・三浦義村や鎌倉幕府第2代執権・北条義時とは従兄弟の間柄になります。彼らの祖父としてみな、伊東祐親がいます。また、それぞれの父・三浦義澄と北条時政はおじにあたります。
「曽我物語」には、曾我祐成と三浦義村は幼少期に伊東で一緒に育てられたという描写もあります。
曾我兄弟は、父の仇である工藤祐経を討つために、このような間柄や三浦一族から得られる情報網も利用していたのでしょう。
なお、この時代のキーパーソンを多数輩出した伊東祐親でしたが、源頼朝による平家討伐の挙兵時は平家方に付き、1180年(治承4年)の富士川の戦いで源氏方に捕らえられ、最期は葉山の鐙摺で自刃または殺害されます。
曾我十郎祐成の子・了源の出家と平塚での開基

やはり、乗誓寺の寺伝によると、出家前の了源は鎌倉幕府第3代将軍(鎌倉殿)・源実朝に武士として仕えていて、多くの武功の恩賞として、平塚の地に所領を得ていたと言います。
しかし、「曾我兄弟の仇討ち」のことでは、いろいろと思うところがあったようです。ちょうど、親鸞聖人が関東で布教活動を行っていた際にその教えに帰依することとなり、鎌倉時代中期の1227年(安貞元年)、出家した了源は、親鸞聖人直筆の十字尊号を本尊として、平塚に阿弥陀寺を開きました。
その後、室町時代中期の1467年(応仁元年)に発生した応仁の乱によって世の中が不安定になると、戦乱を避けて、1469年(文明元年)、阿弥陀寺は時の住職・空浄によって平塚から浦賀に移されました。
平塚という土地は、了源の母・虎御前の出身地であると同時に、三浦一族とも関係が深い土地です。
了源が平塚に阿弥陀寺を建立した当時で言えば、三浦義村が平塚の田村に拠点を持っていました。その少し前には、三浦氏宗家第4代当主・三浦大介義明の弟・義実が現在の伊勢原市との境にある岡崎を領し、岡崎氏を称しました。
空浄が寺を平塚から浦賀に移した時期は、岡崎城には相模三浦氏(鎌倉時代中期の宝治合戦による三浦氏宗家滅亡後に再興された三浦一族)の当主・三浦時高が城主になっていて、やはり、三浦一族の影響下にある土地でした。
三浦一族が影響を与えたかどうかは別として、浦賀への移転は、三浦一族の支配地域内での移転ということになります。
この後、三浦氏ゆかりの岡崎城は、相模三浦氏の当主が三浦道寸(義同)の時代に後北条氏に攻められ、三浦半島の先端にあった新井城まで追いやられた道寸とその一族は、そこで最期を迎えることになります。
浦賀のまちの繁栄の当事者となった乗誓寺
平塚より移転した当時の浦賀は、江戸時代に交易で繁栄するようになるよりもかなり前の時代で、小さな港町だったとみられます。戦国時代に後北条氏が房総半島の里見氏に対抗するため浦賀城を築いたのも、もう少し後の時代です。
三浦半島も決して安寧の地というわけではなく、相模三浦氏、後北条氏、そして徳川家康と次々と領主が変わるなか、寒村だった浦賀での寺院運営は厳しいものがあったようですが、江戸時代前期の1615年(元和元年)、時の住職・空覚によって再興されました。
その後、1637年(寛永14年)には、現在の寺号である乗誓寺に改められています。
江戸に幕府が置かれると、その玄関口となった浦賀のまちが繁栄していく様子を、乗誓寺も当事者として見ていくことになります。徳川家康に仕えた幕府の代官頭・長谷川長綱は浦賀に陣屋を構え、いわば国策として浦賀の港を整備していきました。
江戸時代前期には、房総半島産の干鰯(鰯などを使った魚肥)を扱う問屋や廻船問屋の発展がまちを潤しました。江戸時代中期の1720年(享保5年)には浦賀奉行所が置かれることになり、浦賀の賑わいは最盛期を迎えることになります。
乗誓寺の墓地には、この江戸時代の浦賀の発展を象徴するかのように、豪商たちの大きな墓が並んでいます。
なかでも、浦賀の干鰯問屋の代表格であった「宮与(宮原屋)」の宮井与右衛門一族の墓所はとくに立派です。宮井与右衛門は代々の通り名で、紀州・宮原(現在の和歌山県有田市)から浦賀に移住し、干鰯問屋として成功をおさめた豪商です。東浦賀村の年寄役や明治時代には浦賀町の町長を務めるなど、江戸時代から明治期にかけての宮井与右衛門は、政治的にも浦賀の中心的な人物の一人でした。
また、江戸時代の乗誓寺は学問所としての役割も担っていたと言い、詩画僧・雲室、二宮尊徳、大隈重信らが講義をしたと伝えられています。
この流れをくみ、明治初期には、乗誓寺に浦賀小学校の前身にあたる郷学校が開校しています。


乗誓寺は枝垂れ桜の名所
現在の乗誓寺は、春の枝垂れ桜が見事です。それは、往時の浦賀のまちの繁栄を偲ばされるようでもあります。


乗誓寺周辺の見どころ