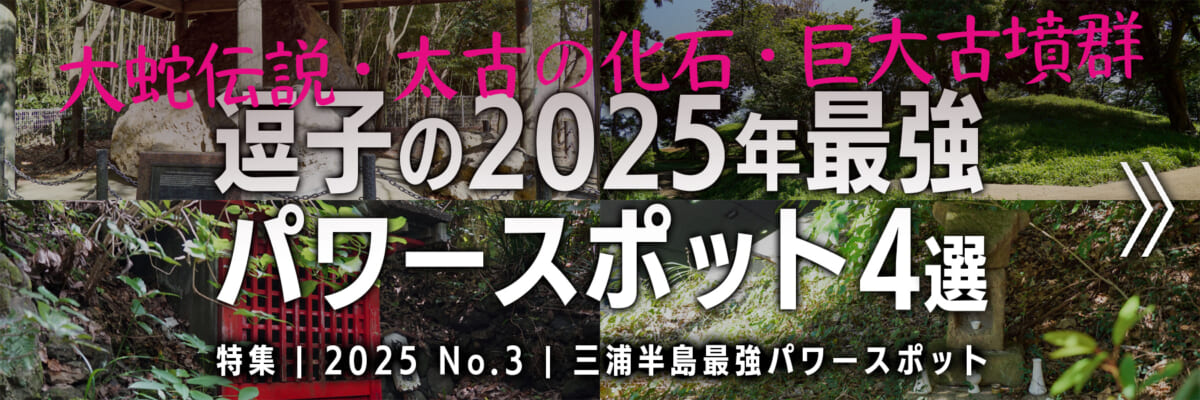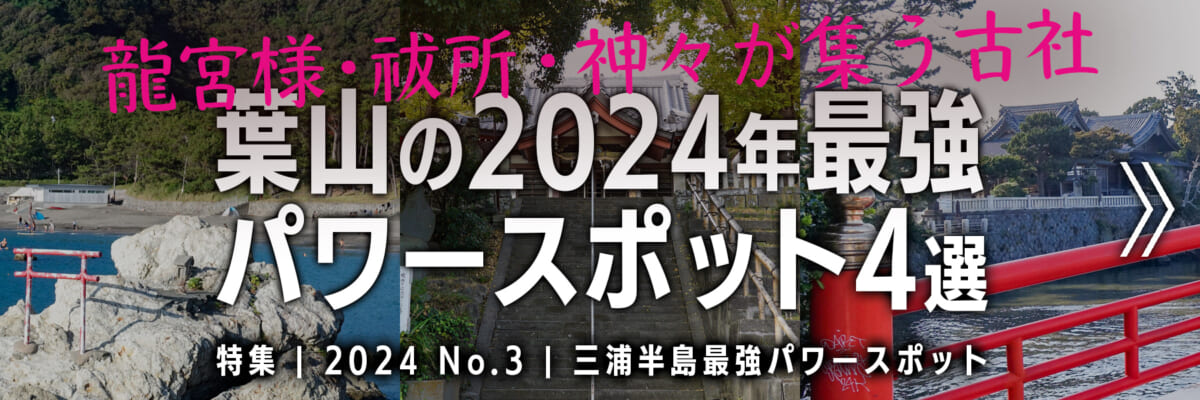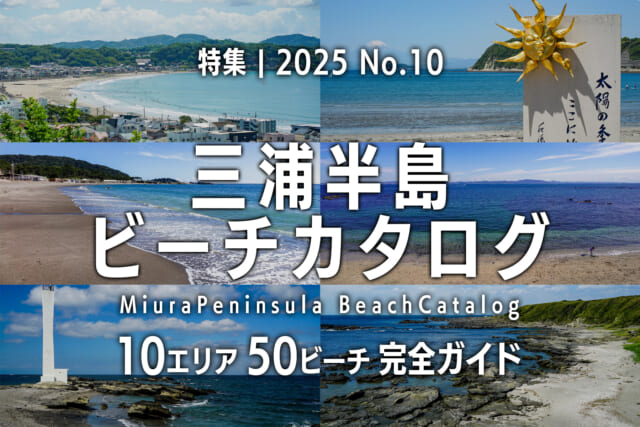長柄桜山古墳群は、逗子市と葉山町にまたがる丘陵地にある前方後円墳で、現存する神奈川県内の古墳としては最大級のものです。
葉桜住宅の西端近くに第1号墳、蘆花記念公園の裏山にあたる場所に第2号墳の、2基の前方後円墳が確認されています。第1号墳と第2号墳の間の距離は500mほどで、「ふれあいロード」と名づけられた尾根道で結ばれています。
2基とも古墳時代前期(4世紀)のものと推定されていて、多くの埴輪や土器などの埋葬品が発見されています。
長柄桜山古墳群の存在が知られるようになったのは比較的近年のことで、1999年に地元の考古学愛好家によって第1号墳が発見され、同じ年に第2号墳の存在も確認されました。
それまで三浦半島で見つかっていた前方後円墳は、大塚山古墳群や蓼原古墳など、久里浜周辺(古久里浜湾)に集中していました。三浦半島の付け根部分は前方後円墳の空白地帯とされていましたが、この地域にも有力な豪族が存在する重要な拠点があったことが確認されたことになります。
長柄桜山古墳群は、この地域の文化遺産という意味はもとより、当時の中央政権(ヤマト政権)と関東地方とのかかわりを知るうえでも貴重な存在であることから、2002年に国の史跡に指定されました。
INDEX
海上交通の拠点を治めていた首長の墓か?

久里浜周辺の古墳が東京湾に注ぐ三浦半島最大の河川である平作川流域の河口部に点在しているのに対して、長柄桜山古墳群は相模湾に注ぐ田越川流域の河口部の南岸に位置しています。
また、長柄桜山古墳群が発見されるまでは三浦半島の相模湾側で確認されていた唯一の前方後円墳だった経塚古墳(横須賀市長井のソレイユの丘駐車場近く)は、三浦半島の相模湾側で最大の入り江である小田和湾の南岸にあります。
いずれも三浦半島では大きな湾や河川の河口部にあることから、共通点として、そこには、河川や大きな入り江と海を利用した海上交通の拠点があったことが推測されます。
古代、田越川沿いには、古東海道(律令時代の畿内から常陸国に至る官道で、相模国と上総国の間は、鎌倉、逗子、葉山から三浦半島を東西に横断して、走水付近より海路で房総半島に渡るというルートだったと考えられています)のルートの一つが走っていたと考えられています。
古東海道沿いにあり、相模湾から田越川を利用した海上交通の要衝にあたるこの地に、当時の関東地方の有力者の拠点があったとしても、不思議なことではありません。
古代からの人間の営みの痕跡が多く残る田越川流域
その存在が認知されるようになった時期に差が出た理由でもありますが、久里浜周辺の古墳が開発によってすでにその多くが失われてしまったり原型をとどめていないのに対して、開発の手を免れてきた長柄桜山古墳群は良好な形でほぼ原型をとどめていると考えられています。
そのため、長柄桜山古墳群では、今後の発掘調査によって当時の三浦半島地域がどのような役割を担っていたのか、より明確になっていくことが期待されます。
これまでの長柄桜山古墳群の発掘調査で発見された埴輪や土器などの出土品の一部は、池子の森自然公園内にある池子遺跡群資料館と、葉山しおさい公園内にある葉山しおさい博物館で展示されています。


また、長柄桜山古墳群と同じ田越川流域の南岸には持田遺跡が、対岸の北側には池子遺跡群が存在することが知られていて、ともに長柄桜山古墳群に前方後円墳が造られたころの生活の痕跡が見つかっています。

長柄桜山古墳群・第1号墳と第2号墳の現況

長柄桜山古墳群・第1号墳は、発掘調査終了後、保護盛土などによって遺構の保存や周辺環境の整備がなされ、2024年4月から古墳の本体にあたる墳丘の一般公開が開始されました。
第1号墳と第2号墳それぞれの詳細は、以下のリンク先よりご覧ください。
長柄桜山古墳群・第1号墳と第2号墳とは、ハイキングコース「ふれあいロード」で結ばれています。
長柄桜山古墳群や「ふれあいロード」上にはトイレがなく、最寄りの公衆トイレは、第2号墳のふもとにあたる蘆花記念公園または六代御前の墓近くのものになります。

長柄桜山古墳群関連の特集