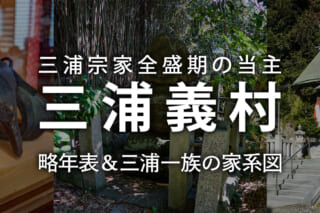京急線汐入駅からほど近い場所に鎮座する子之神社は、横須賀・汐入町の鎮守です。汐入町は旧横須賀村(1876年(明治9年)に町制施行。周辺の町村との合併を経て、1907年(明治40年)に市制施行)の村域にあり、村の総鎮守は諏訪神社(諏訪大神社)でしたが、子之神社は現在のほぼ汐入町にあたる旧汐入・汐留・谷町・湊町(港町)各町のより身近な鎮守として親しまれてきました。
子之神社は鎌倉時代中期に勧請されたと伝わる、旧横須賀村内でももっとも歴史のある神社の一つです。しかし、創建当初の境内が海軍用地(現在の米海軍横須賀基地内)になるなど、明治期に二度の遷宮を余儀なくされることになりました。
横須賀の軍都化という時代の流れに翻弄され続けた子之神社でしたが、神社前の通りに「汐入子之神通り」という愛称が付けられるなど、現在はすっかり地域に根付いた神社であることをうかがい知ることができます。
| 主祭神 | 大己貴命 |
| 旧社格等 | 村社 |
| 創建 | 1220年(承久2年) |
| 祭礼等 | 1月1日 新年祭 2月節分 節分祭 3月第1土曜日 春祭 6月第1土曜日・日曜日 例大祭 12月第1土曜日 秋祭 ※実際の日にちは異なる場合があります |
子之神社が最初に移転した場所は、現在の京急線汐入駅北西の、横須賀港を望む山麓でした。1884年(明治17年)のことです。しかし、この山腹にも海軍の施設に電力を供給するための変電所ができることになり、1898年(明治31年)、現在地に移転することになりました。
最初の移転先には14年しか鎮座していなかったことになりますが、当時の子之神社の裏山は、その後も「子ノ神山」と呼ばれ続けています。
横須賀軍港の拡張が急速に進められたことを物語るエピソードの一つであると同時に、短い時間であっても人々の信仰はその場所に根付くものであることを教えてくれています。
INDEX
現在のベース内にあった旧横須賀村最古級の神社

汐入町の子之神社は、鎌倉時代中期の1220年(承久2年)に勧請され、江戸時代前期の1681年(天和元年)に再建されたと伝えられています。ほど近い場所に鎮座する、横須賀の総鎮守・諏訪大神社の創建は南北朝時代と伝えられていますので、それよりも100年程度は古いことになります。(周辺の、旧公郷村の春日神社や旧不入斗村の御嶽神社は、もう少し古い可能性がありそうです)
なお、日本神話では、諏訪大神社の御祭神・健御名方命と事代主命は、子之神社の御祭神・大己貴命の子とされています。
創建当初の子之神社は、現在の米海軍横須賀基地(ベース)内にあたる、楠ヶ浦・泊(現在の横須賀市泊町)の波島に長源寺(横須賀市汐入町3丁目に現存)とともにあったと言います。波島は、当時の横須賀町の北端にあった島で、現在は周囲が埋め立てられて、陸続きになっています。
しかし、ここが海軍用地となったため、1884年(明治17年)に遷宮されることになりました。
子之神社の創建から明治前期までの歴史は、この程度しか伝えられていません。子之神社に限らず、中世の横須賀村の歴史自体、それほど多くは残されておらず、幕末以降の発展とは対照的に、一寒村に過ぎなかったことがうかがい知れます。
子之神社が創建された鎌倉時代中期で言えば、当時の歴史書「吾妻鏡」の建保三年(1215年)三月大五日条に、北条義時らをお供に、鎌倉幕府第3代将軍(鎌倉殿)源実朝が横須賀へお花見に訪れて、三浦義村一族がもてなしたことが記録されています。このことからも、当時の横須賀は三浦義村一族の領地だったとみられます。陸上交通が発達していなかった当時は、舟での移動が多かったはずで、横須賀の岬の突端という要衝にあった波島への神社の勧請に、三浦義村ら三浦一族の武将が関与していた可能性もじゅうぶん考えられるでしょう。
三浦半島の「子ノ神社」一覧
「子ノ神社(子之神社)」という名前の神社は、全国的にはマイナーな存在ですが、南関東ではそれほどでもありません。
江戸時代後期に編さんされた地誌「新編相模国風土記稿」と1879年(明治12年)から1920年(大正9年)にかけて神奈川県がまとめた「明治12年 神社明細帳(三浦郡)」によれば、江戸時代後期から明治期にかけての三浦半島(旧三浦郡のみ。旧鎌倉郡、旧久良岐郡は除く)には、以下のとおり少なくとも11社(または12社)の「子ノ神社」がありました。このうち、現在も「子ノ神社」として存続しているのは、汐入町の子之神社と逗子・小坪の子之神社、逗子・桜山の子ノ神社の3社です。
| 神社名 | 子ノ神社 として現存 | 鎮座地 | 御祭神 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 子ノ神社 | ○ | 横須賀楠ヶ浦 →横須賀汐入町 | 大己貴命 | |
| 子ノ神社 | 横須賀村 | 「新編相模国風土記稿」によると、江戸時代後期の横須賀村には子ノ神社が2社鎮座。 「明治12年 神社明細帳(三浦郡)」には、承久2年勧請・天和元年再建の汐入町の子ノ神社と承久3年勧請・天和元年再建の楠ヶ浦町の子ノ神社がみえる。 昭和初期に発行された「横須賀市内神社略説」によると、承久3年勧請の楠ヶ浦町の子ノ神社(汐入町の子ノ神社とは別の神社という記載)が、1907年(明治40年)、村社「諏訪神社(現在の諏訪大神社)」に合祀されたとある。 | ||
| 子神社 | 長浦村 | |||
| 子ノ神社 | 逸見村字七番 | 大己貴命 | 1908年(明治41年)、村社「鹿島神社」に合祀。 | |
| 子ノ神社 | 野比村字大作 | 豊斟渟尊 | 1908年(明治41年)、村社「白髭神社」に合祀。 | |
| 根神社 →子ノ神社 | 上宮田村字根元 | 大己貴命 | ||
| 子ノ神社 →飯森社 | 下宮田村字飯森 | 大己貴命 | 妙音寺持。大黒天石像を安置。 1908年(明治41年)に「姥神社」と合併して「飯森社」と改称。 | |
| 小坪根神 →子ノ神社 | ○ | 小坪村 | 昭和初期に発行された「逗子町誌」によると、小坪の中里と谷戸の鎮守で、祭神・大国主命の木像を安置するとあり。 | |
| 子ノ神社 | ○ | 桜山村 | 大國主命 | 金剛寺持。 村社「神明社」に合祀された後、現在は「子ノ神社」として存続。 |
| 子ノ神社 | 長柄村 | 仙光院持。 | ||
| 子ノ神 →柏原明神社 →稲荷神社 →久木神社 | 柏原村 | 江戸時代中期の元禄年間に「子ノ神」から「柏原明神社」に改称。 1874年(明治7年)に柏原村は久野谷村と合併して久木村となり、1882年(明治15年)に村内の神社を村社「稲荷神社」に合祀。 「稲荷神社」は1970年(昭和45年)に「久木神社」へ改称。 | ||
| 子ノ神 | 池子村 | 1877年(明治10年)、村社「神明社」に合祀。 |
大国主の神話と「子ノ神社」という神社名の由来

「子ノ神社(子之神社)」という一風変わった神社名の由来は、十二支の一つである「子(ね)」から名づけられたものなのでしょう。「子」は動物で言うとネズミ、方角で言うと北を指します。
汐入町の子之神社は、創建当初は横須賀村の北端にありましたので、村の北側、もしくはなんらかの施設の北を守るという意味合いで、方角の北から名づけられた可能性も否定できません。
しかし、他社に合祀されたものを含め、汐入町の子之神社をはじめ、三浦半島の「子ノ神社」の多くで、主祭神として大己貴命(大国主、大国主神など多くの別名が存在)が祀られていることを考えれば、神社名と大己貴命の間に関連性があると考えるのが自然です。そして、大己貴命(大国主)の神使はネズミと考えられているため、このことが由来である可能性が高そうです。
古代の歴史書「古事記」には、大国主の神話として「根の国」という場所が登場します。ここで大国主は須佐之男命(スサノオ)の火攻めにあい、焼き殺されそうになりますが、ネズミの助言によって地面の下の穴に隠れることができ、難を逃れることができました。
このことから、ネズミは大国主の使いとされるようになりました。
ネズミの語源には、根の国に住む生き物、あるいは、単に暗い場所に住む生き物として、「根棲み」という説があります。
小坪村の子ノ神社がかつて「小坪根神」と呼ばれていたり、上宮田村の子ノ神社の旧社名が「根神社」だったりするのは(鎮座地の地名は「根元」)、「根棲み=ネズミ」が由来で、時代とともに、よりポピュラーな「子」という漢字をあてるように変化していったと考えられます。
また、明治維新より前の神仏習合の時代、同じ「ダイコクさま」として、大己貴命(大国主)は七福神の一柱・大黒天と同一視されていました。廃仏毀釈によって現在ではその痕跡が残っていないことが多いですが、下宮田村の子ノ神社(現在の飯森神社)に大黒天石像が安置されていたのが分かりやすいケースです。
大己貴命あるいは大黒天は、一般的に、五穀農穣の神や商売繁盛の神、医療の神などとされています。これらを信仰する神社として、大己貴命あるいは大黒天が祀られる(付会される)ようになり、そのいくつかは「子ノ神社」と名付けられたものと考えられます。
なお、かつて、鎌倉・山ノ内の建長寺には四方鎮守があって、東に八幡、北に熊野、西に子神、南に第六天が祀られていたと言います(現存するのは第六天のみ)。ただし、この建長寺の例では、子ノ神は北ではなく、西の方角にあります。
建長寺と同じように、横須賀村の南端にも第六天(現在、横須賀市坂本町2丁目に鎮座する大六天神社)が祀られています。このように、子ノ神と第六天はセットで祀られることもあったようですが、三浦半島では、建長寺と横須賀村の他は桜山村でみられる程度で、子ノ神社全体の数に比べると必ずしも多いとは言えず、強い相関は認められません。
汐入町の鎮守としてまちをあげて執り行われる例大祭

汐入町の子之神社の例大祭は、例年、6月第1土曜日・日曜日に執り行われます。汐入町の各町内の御神輿や山車が町内を巡行する他、京急線汐入駅近くの汐留通りを歩行者天国にした屋台の出店などがあり、まち中が賑やかになります。(内容は年によって異なる場合があります)


汐入子之神社のその他の見どころ



汐入子之神社周辺の見どころ