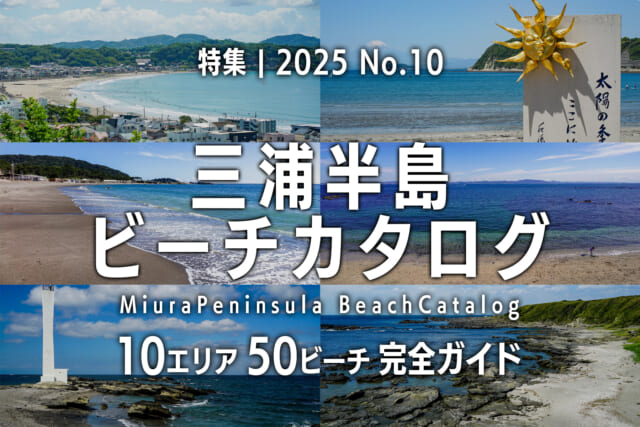極楽寺は、江ノ電「極楽寺駅」のすぐそばに建つ茅葺の山門が風情たっぷりの、真言律宗の寺院です。「鎌倉七口」の一つである極楽寺坂切通の、西側(鎌倉の中心市街から見て外側)の入口にあたる場所にあります。
山門のすぐ近くには、江ノ電で唯一のトンネルである極楽洞(極楽寺トンネル)があります。
極楽寺は、京都や東海道方面からの鎌倉の入口という重要な場所にあることや、元寇の際には幕府の命令によって忍性が異国退散の祈祷を行うなど、鎌倉幕府から信頼と保護を受けていました。
開基の北条重時は、鎌倉幕府第2代執権・北条義時の子です。母の姫の前は比企一族出身ですが、比企能員の変で北条時政・義時らによって一族が滅ぼされたため、後に義時とは離縁しています。
| 山号 | 霊鷲山 |
| 宗派 | 真言律宗 |
| 寺格 | ― |
| 本尊 | 釈迦如来 |
| 創建 | 1259年(正元元年) |
| 開基 | 北条重時 |
| 開山 | 忍性 ※1267年(文永4年)に入山した実質的な開山 |
極楽寺は、最盛期には七堂伽藍と49院の塔頭を構える大寺院でした。その中には病院や福祉施設などもありました。現在はそのほとんどが火災や自然災害などによって失われてしまいましたが、山門とその前で咲く梅や山門と本堂の間にある桜並木の参道などは風情があり、往時をしのばせてくれます。

INDEX
「地獄」に建てられた 極楽寺

極楽寺が建立された場所は、その当時、「極楽」どころか「地獄」と呼ばれていたような場所でした。行き場を失った者が集まったり、庶民が死体を埋葬したり遺棄したりするような場所でした。
このような場所は、巨福呂坂に近い建長寺周辺や名越切通にあるまんだら堂やぐら群周辺などの、極楽寺と同じような他の鎌倉の周辺部にも伝承が残っています。極楽寺や建長寺・回春院のあたりは、「地獄谷」とも呼ばれていました。
このような場所に寺院が建てられたのは、死者を供養する目的もあったと考えられます。


奥の院に建つ忍性の墓と伝わる忍性塔

極楽寺は、最盛期の室町時代には、現在の境内の裏に位置する稲村ヶ崎小学校やその背後の敷地まで境内に含まれる大寺院でしたが、火災や自然災害などによって衰退していき、現在は山門と本堂などが存在するのみです。
稲村ヶ崎小学校の裏手には忍性の墓と伝わる忍性塔(1年に一度、4月8日に公開。撮影禁止)がありますが、このあたりまでが寺域だったと考えられています。現在、この忍性塔の建つあたりは、極楽寺の「奥の院」と呼ばれています。
忍性塔は鎌倉後期に建立されたと見られる石造五輪塔で、国の重要文化財に指定されています。3m以上もある巨大な五輪塔で、間近で見るとものすごい存在感があります。


忍性が境内に病院や慈善施設などを整備
極楽寺の実質的な開山である忍性は、この広い境内のなかで、道場の他に、療病院という病院施設や、悲田院という身寄りのない者を収容して救済する施設などを整備するなど、慈善活動にも尽力しました。
現在の境内周辺には「寺中」という地名(旧字名、現在の極楽寺3丁目付近)がついていましたが、その北側の谷戸には「馬場ヶ谷」という名前がつけられました。これは、極楽寺坂切通を下った反対側にあたる坂ノ下にあった馬用の病舎で治療した馬の調整をしていたことにちなむと言われています。
極楽寺の病院としての機能は、人間のためだけのものに留まらず、中世には重要な交通手段であり戦の相棒だった馬にもやさしい寺院だったことをうかがい知ることができる逸話です。
慈善活動に積極的だった忍性は、鎌倉幕府の実権を握っていた執権北条氏のあつい庇護を受けて、当時の鎌倉を代表する僧の一人でした。当時としてはめずらしく、仏教の力だけでなく、薬学という最先端でテクニカルな手法も用いていたことが、信頼につながっていたのかもしれません。
また、忍性は経営者としての才能も高かったようです。鎌倉の貿易港として現在の材木座海岸の沖合に築かれた和賀江嶋(和賀江島)は、忍性の時代に極楽寺が運営や維持・管理などの経営権を持つようになったと伝えられています。
製薬鉢と千服茶臼

極楽寺の本堂の前には、忍性が施薬に使用したものと伝わる、「製薬鉢」と「千服茶臼」が残されています。

極楽寺の井

病院や慈善施設の運営には、多くの水を必要としたはずです。極楽寺の山門の前からは鎌倉石を8段積み上げて作られていたという大きな井戸が発見されていて、忍性はこの井戸の水を使用して粥を施していたと伝えられています。
「極楽」のような桜並木の参道

ソメイヨシノの桜のトンネル
現在、茅葺屋根の山門から本堂まで続く極楽寺の参道は、桜並木になっています。
極楽寺の参道はそれほど広くはないため、毎年春には桜のトンネルができあがります。かつて「地獄」のような場所だったとは想像できない「極楽」のような華やかさに包まれます。


八重一重咲分け桜(桐ヶ谷桜)
桜並木の奥のほうには、鎌倉幕府第8代執権・北条時宗お手植えの桜から派生したものと伝わる、八重一重咲分け桜(桐ヶ谷桜、御車返し)があります。1枝に八重と一重の花が混在して咲く、めずらしい品種で、鎌倉・桐ヶ谷が原産とされています。

▼その他の鎌倉の桜の名所はこちら▼
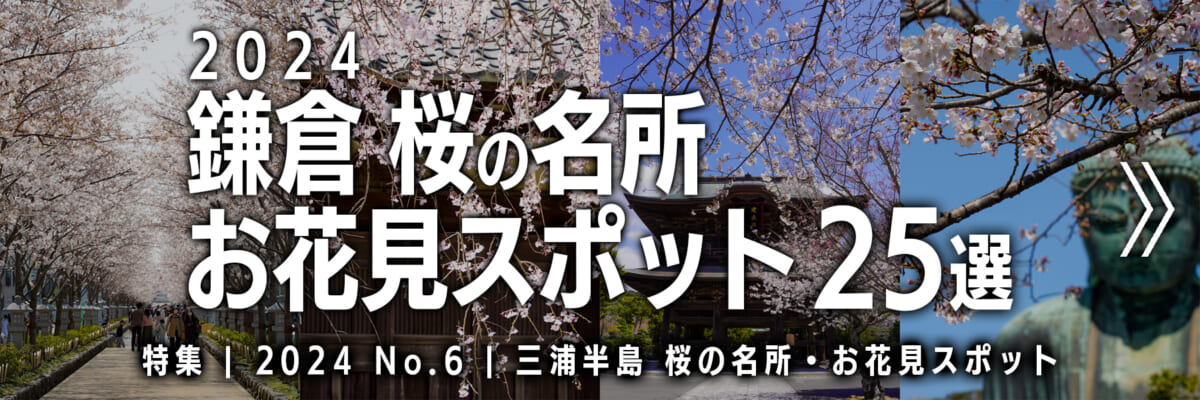
茅葺の山門と相性バツグンの極楽寺のあじさい

極楽寺の山門前には、あじさいが植栽されています。例年、6月上旬前後に開花すると、茅葺の山門とあじさいが、極楽寺ならではの風景をつくりだしてくれます。
極楽寺では、山門周辺以外でも、境内の各所であじさいを見られます。


▼その他の鎌倉のあじさいの名所はこちら▼

子育てにご利益がある みちびき地蔵

極楽寺の山門から境内を出て極楽洞(極楽寺トンネル)や極楽寺坂切通方面に向かうと、正面に赤い屋根の古い建物が見えます。
ここは、縁側がちょっとした休憩スポットにもなっている導地蔵堂で、子育てにご利益があると言われる導地蔵が安置されています。導地蔵堂は、忍性が運慶作の地蔵を安置したのがはじまりと伝えられています。
この導地蔵は、鎌倉二十四地蔵の一つ(第20番)に数えられています。
子育てにご利益のあるお地蔵様としては、極楽寺境内の本堂前でも子育地蔵尊が出迎えてくれます。

極楽寺周辺の見どころ