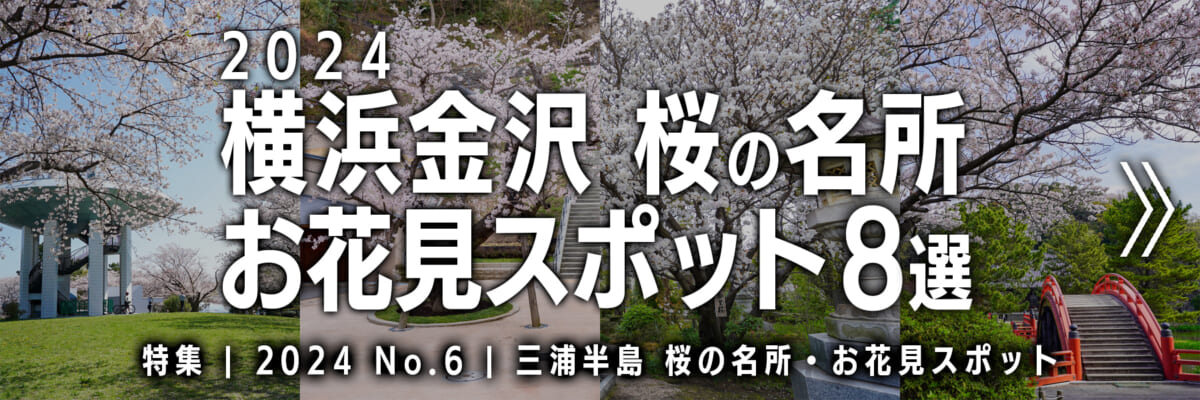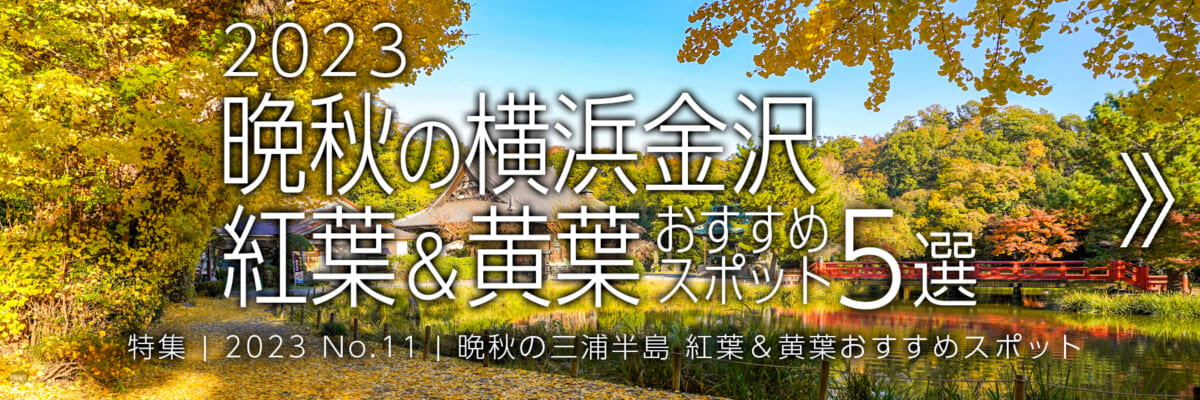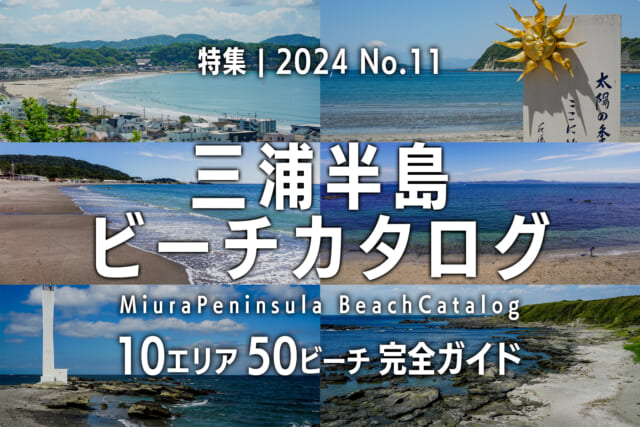称名寺は、北条実時が建立した金沢北条氏の菩提寺です。
文化人としても知られた実時は、隣接地に、日本最古の武家文庫である金沢文庫を設けています。
仁王門から庭園に入って、阿字ヶ池にかかる反橋、中島、平橋を渡り金堂に至る浄土式庭園は、1323(元亨3年)に描かれた「称名寺絵図」に基づいて1987年(昭和62年)に復元されたもので、国の史跡に指定されています。
とくに、春の桜の季節と、晩秋の紅葉・黄葉の季節は、まさに極楽浄土に迷い込んだかのような、美しい世界がひろがります。
称名寺の塔頭である光明院には、運慶仏の真作と認められている大威徳明王坐像が伝わっています。この大威徳明王坐像は、近年(2007年)運慶作であることが確認された仏像で、現存する運慶仏の中では最晩年の作品とされています。
| 山号 | 金沢山 |
| 宗派 | 真言律宗 |
| 寺格 | 別格本山 |
| 本尊 | 弥勒菩薩立像 |
| 創建 | 1259年(正元元年)ごろ |
| 開山 | 審海 |
| 開基 | 北条実時 |
称名寺は、武蔵国久良岐郡六浦荘(現在の横浜市金沢区六浦周辺から金沢文庫駅周辺にかけて。かつては、六浦荘金沢というように、金沢と六浦の行政区画は上下関係が現在と逆でした)の領主となった金沢北条氏の居館が前身です。
六浦は鎌倉幕府の外港・貿易港として栄えた幕府の重要な拠点の一つで、1241年(仁治2年)ごろに鎌倉との間に朝夷奈切通が開削されて六浦道(現在の金沢街道)が整備されると、地理的にも政治的にもより重要な場所として開発されていくことになります。
INDEX
かつては七堂伽藍を備えた壮麗な伽藍だった

称名寺は、最盛期だった北条貞顕(金沢貞顕)の代の頃(1300年代前半)には、中央の池を囲むように、金堂や講堂、鐘楼、仁王門など七堂伽藍を備えた壮麗な伽藍だったと伝わっています。
しかし、鎌倉幕府の滅亡によって金沢北条氏も滅んだ後は伽藍の維持ができなくなり、衰退が進みました。現在の建造物の多くは、江戸時代に再建されたものです。




『金沢八景』の一つ「称名晩鐘」

江戸時代に歌川広重によって描かれた『金沢八景』の「称名晩鐘」は、小舟の上に立つ人が、夕暮れに響く称名寺の鐘の音に向かってお祈りする様子が描かれています。
「かながわの橋100選」に選定されている平橋と反橋

称名寺の平橋と反橋は、「かながわの橋100選」に選定されています。
浄土式庭園の池にかかる朱色の橋は、仁王門と金堂を結ぶ参道の一部として、実際に渡ることができます。
称名寺の桜
赤門から仁王門までの称名寺桜並木

惣門(赤門)から仁王門まで続く称名寺の参道は、桜並木になっています。通りが狭いため、桜のトンネルをたのしめます。例年、開花時期の夜はライトアップされて、夜桜もたのしめます。
※称名寺の桜並木は2023年に大きく剪定されたため、2024年春以降は少しボリュームが小さくなることが予想されます。


浄土式庭園と称名寺市民の森の桜
阿字ヶ池のまわりや裏山の称名寺市民の森にも、何本もの桜の木が植栽されています。普段の浄土式庭園の主役は、朱色の平橋と反橋ですが、この時期だけは桜が主役の座に躍り出ます。


称名寺のライトアップ

称名寺では、夜桜以外にも、薪能といったイベント開催時にあわせて境内各所がライトアップされることがあります。朱色の平橋と反橋は、ライトアップされるとより一層その美しさが増します。

称名寺の黄葉&紅葉
どこをどう切り取っても絵になる晩秋の浄土式庭園

称名寺には、阿字ヶ池のほとりや仁王門の近くに、立派な大イチョウが何本も立っています。晩秋には、黄金色に色づいて、最盛期にはイチョウのじゅうたんで敷きつめられます。モミジもありますので、称名寺では黄葉も紅葉もたのしめます。
もともと上質な絵画のような風景をたのしめる称名寺の浄土式庭園ですが、黄葉・紅葉の時期はとくに、切り取り方次第でいろいろな表情を見せてくれます。


大イチョウと阿字ヶ池の鏡面反射

風が穏やかで、鳥たちが遊泳中でなければ、阿字ヶ池に鏡面反射する大イチョウも、晩秋の称名寺の見どころの一つです。黄金色に色づくイチョウと、朱色の反橋がよく映えます。

晩秋の大ケヤキとカイノキ

晩秋の称名寺でたのしめるのはイチョウやモミジの黄葉・紅葉だけではありません。
大イチョウの隣りにそびえる大ケヤキは、その美しい樹形を一年を通して見せてくれますが、晩秋に、控えめに紅葉する姿がもっともケヤキらしさをたのしめる季節かもしれません。
その称名寺市民の森、県立金沢文庫側に立つ、横浜や三浦半島周辺ではあまり見かけない大木は、一般的にはカイノキ(楷の木、楷樹)と呼ばれる木で、1939年(昭和14年)に植えられたものです。晩秋には、美しい紅葉のグラデーションを見せてくれます。
カイノキは、植物学者・牧野富太郎によってクシノキ(孔子の木)とも名付けられています。中国の思想家で儒教の祖である孔子の墓所に植えられていて、孔子にゆかりが深いことから、「学問の木」とも呼ばれています。
かつて、武家のための文庫「金沢文庫」があったこの地にもふさわしい樹木と言えます。

北条顕時・貞顕の墓

称名寺の伽藍や庭園を整備した開基・北条実時の子・顕時、孫・貞顕の墓は、金沢山を背にした境内に並んで建っています。
墓所の柵にある古い石柱には、向かって右側の五輪塔が金沢貞顕(北条貞顕)の墓で、左側の五輪塔が北条顕時の墓と刻まれていますが、1935年(昭和10年)に右の五輪塔から発見された青磁壺の様式等から、実際には左右逆であることが分かっています。

境内の裏に広がる称名寺市民の森

称名寺の裏手の金沢三山(金沢山・稲荷山・日向山)は、境内背後を囲むように称名寺市民の森として整備されていて、境内からも入ることができます。約10ヘクタールに及ぶ緑地は、市民の憩いの場所になっています。
称名寺市民の森内には、称名寺を建立した北条実時とその一門の墓があります。
※北条実時の墓は、厳密には称名寺市民の森の範囲外にあり、所有者は称名寺になりますが、市民の森とあわせて訪れる方が多いと考えられることから、市民の森のページで紹介させていただいております。
関連施設

称名寺と県立金沢文庫は、短いトンネルで結ばれています。


称名寺周辺の見どころ






称名寺関連の特集記事